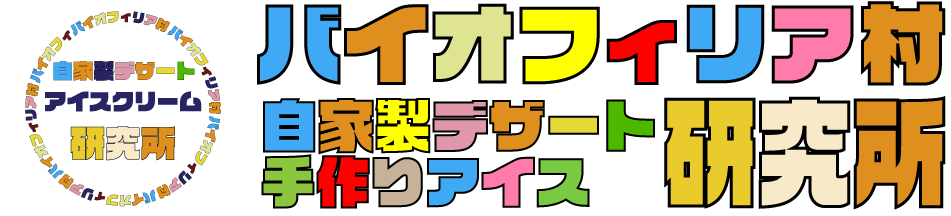バイオフィリア村 製菓部
バイオフィリア村 製菓部
こんにちは!
このページでは、今まで紹介した『クリームソーダとメロンソーダ』に関する記事や動画をまとめていきます。
以下のように↓


動画やテロップを用いながら、かなり細かい所まで丁寧にまとめていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみて下さい!
クリームソーダ作りで意識するポイントと注意点
こちらの動画に、クリームソーダを作る時のポイントと注意点をまとめて紹介しました!
主なポイントと注意点は以下の通りです↓
【ポイント】
①:使用する道具は、このページで紹介したものを参考にして下さい!
②:製氷器の氷までこだわり、氷は多めにしてソーダ水を作る!
⇒氷が少ないとソーダ水が美味しくないので、氷を多めでキンキンに冷やして飲むようにして下さい!
③:シロップと炭酸水の比は、3:7くらいのバランスがオススメ!
④:アイスは、スクープとディッシャーで結構形が変わってくるので、お好みの方を使いましょう!
⑤:炭酸水を先に入れるとシロップ量のコントロールが難しくなるので、シロップを先に入れ、その後に炭酸水を入れるのがオススメ!
【注意点】
①:炭酸水の入れすぎに注意!
⇒アイスを入れる前に炭酸水を入れ過ぎてしまうと、アイス投入時にこぼれてしまうので気を付けましょう!
②:アイスを入れた後でマドラーでかき混ぜるのは難しい…(こぼれる可能性が高いので)
⇒アイスを乗せる前のソーダ水が完成した段階で、マドラーでよくかき混ぜると良い!
③:アイスを下に押し込むとソーダ水があふれ出してしまうので、絶対にアイスを下に押し込まないように!
まずは、この動画からご覧ください。
過去記事がこちら!
 【厳選!道具まで含めて徹底解説!】クリームソーダの作り方とオススメ道具について解説!!【メロンソーダで作る】
【厳選!道具まで含めて徹底解説!】クリームソーダの作り方とオススメ道具について解説!!【メロンソーダで作る】
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
メロンソーダ用のメロンシロップは、老舗のコレがオススメ!!
「メロンシロップ」-1024x576.jpg)
メロンソーダを作りたい時は、こちらのメロンシロップがオススメです!
中村商店(キャプテン)という喫茶店などにも商品を卸している老舗のシロップメーカーの商品です。

シロップと炭酸水を混ぜるだけなので簡単に作れますよ♪
解説動画がこちら!
詳しくは、こちらの過去動画をご覧ください。
過去記事がこちら!
 【手軽に純喫茶風メロンソーダ!】簡単にメロンソーダが作れるキャプテンの「メロンシロップ」を紹介!!【中村商店】
【手軽に純喫茶風メロンソーダ!】簡単にメロンソーダが作れるキャプテンの「メロンシロップ」を紹介!!【中村商店】
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
ブルーのクリームソーダ用シロップは、コレがオススメ!!

ブルーのクリームソーダを作りたい時は、こちらのシロップを使用するのがオススメです!

このシロップも他と同様に、シロップと炭酸水を3:7くらいの割合で混ぜるだけでOKです!
解説動画がこちら!
詳しくは、こちらの過去動画をご覧ください。
過去記事がこちら!
 【唯一無二の発色!!】ブルーのソーダ水が作れるキャプテンの「ブルーシロップ」を紹介!!【中村商店】
【唯一無二の発色!!】ブルーのソーダ水が作れるキャプテンの「ブルーシロップ」を紹介!!【中村商店】
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
【補足】カクテル用のブルーシロップ(ブルーキュラソー)は、残念ながらクリームソーダには合いません…

ブルーシロップというと、上の写真の右側『カクテル用のブルーキュラソー』のような商品もありますが、実際にこのシロップでクリームソーダを作ってみたら、美味しくありませんでした汗。
このシロップが悪いというより、『カクテル用はカクテル用』として使うのがベストといった感じですかね。
なので、クリームソーダやソーダ水に関しては、キャプテンのブルーシロップを使う方が良いです。
赤いクリームソーダの作り方

こちらのシロップを使用する事で、赤いクリームソーダを作る事が可能です!

イチゴ味とありますが、そこまでイチゴの風味が強くないので、普通にクリームソーダ用のシロップとして使っていけます!
解説動画がこちら!
詳しくは、こちらの過去動画をご覧ください。
過去記事がこちら!
 【動画で解説!】赤いクリームソーダの作り方を紹介!!
【動画で解説!】赤いクリームソーダの作り方を紹介!!
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
クリームソーダやメロンソーダ用として一番オススメのジュースグラス!!

クリームソーダやメロンソーダ用のジュースグラスは、こちらの商品が一番オススメです!
自分も色々なグラスを持っていますが↓

クリームソーダやメロンソーダを作る時は、ほぼこのグラスしか使っていません笑。
『見た目の収まりの良さ・値段の買いやすさ・アイスとの相性・量の使いやすさ』の四拍子揃ったアイテムです。
解説動画がこちら!
詳しくは、こちらの過去動画をご覧ください。
過去記事がこちら!
 【最強のクリームソーダグラス!!】クリームソーダやメロンソーダ用としてオススメの「ジュースグラス (カップ)」を紹介!!
【最強のクリームソーダグラス!!】クリームソーダやメロンソーダ用としてオススメの「ジュースグラス (カップ)」を紹介!!
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
クリームソーダやメロンソーダ用の氷なら、この製氷器で作るのがオススメ!!

クリームソーダやメロンソーダを作りたい時に使う氷は、こちらの製氷器で作るのがオススメです!
-1024x576.jpg)
『氷なんてどれも一緒じゃない??』と思う方もいるかもしれませんが、氷ひとつ取って見ても、アイスが乗せやすくなったり、冷凍庫の臭い移りの削減など、色々なメリットがあるので、皆様にも製氷器までこだわって欲しいと思っております。
ちなみに余談ですが、氷なしで作るシロップジュースはあまり美味しくないので、氷を大量に入れるのは必須だと思っておいてください。
解説動画がこちら!
詳しくは、こちらの過去動画をご覧ください。
過去記事がこちら!
 【タッパーふたでニオイ移り解消!!】氷のニオイ移りが気になる方にオススメのエビス「ブロックアイストレー家庭用製氷器」を紹介!!
【タッパーふたでニオイ移り解消!!】氷のニオイ移りが気になる方にオススメのエビス「ブロックアイストレー家庭用製氷器」を紹介!!
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
クリームソーダやメロンソーダ用のマドラーは、柳宗理がオススメ!!

クリームソーダやメロンソーダを作りたい時に使うマドラーは、こちらの柳宗理のものがオススメです!

値段もそこまで高くはなく、シンプルでありながら素材感が良いので使いやすいです。

100均のダイソーでもマドラーを購入する事が出来ますが、このように、エッジの処理や素材感に大きな違いがあります。
ですので、よりこだわりたい方は、柳宗理のマドラーを使うと良いでしょう!
解説動画がこちら!
詳しくは、こちらの過去動画をご覧ください。
過去記事がこちら!
 【100均と比較しながら解説!】柳宗理のマドラーをダイソーのマドラーと比較しながら紹介!!
【100均と比較しながら解説!】柳宗理のマドラーをダイソーのマドラーと比較しながら紹介!!
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
【補足】100均ダイソーのマドラーの解説がこちら!
ダイソーのマドラーの方が気になるという方は、こちらの動画を参考にしてみて下さい。
過去記事がこちら!
 【100円で買える日本製マドラー!】100均のダイソーで購入できる「マドラースプーン」を紹介!!
【100円で買える日本製マドラー!】100均のダイソーで購入できる「マドラースプーン」を紹介!!
過去記事はこちらです。
【実はオススメ】柚子(ゆず)シロップを使ったクリームソーダが地味にオススメです!

こちらの柚子(ゆず)シロップが地味に美味しくて、クリームソーダにもオススメです♪
ほとんど知名度はないんですけどね笑

このように、見栄えも良くて味も良いクリームソーダが作れるので、皆さんもぜひ試してみて下さい!
解説動画がこちら!
詳しくは、こちらの過去動画をご覧ください。
過去記事がこちら!
 【個人的にBest 3!!】柚子(ゆず)系のジュースが作れるキャプテンの「柚子シロップ」を紹介!!【中村商店】
【個人的にBest 3!!】柚子(ゆず)系のジュースが作れるキャプテンの「柚子シロップ」を紹介!!【中村商店】
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
【メロンソーダの亜種!】レッドメロンソーダという飲み物も作れる!!【ハロウィンにオススメ!】

メロンの亜種として、こういった『レッドメロン』という味のシロップも発売されています。

メロンとは、味も色味も違うので、詳しくは以下の動画をご覧ください!
解説動画がこちら!
詳しくは、こちらの過去動画をご覧ください。
過去記事がこちら!
 【メロンソーダとの比較も!】レッドメロンのソーダ水が作れるキャプテンの「レッドメロンシロップ」を紹介!!【中村商店】
【メロンソーダとの比較も!】レッドメロンのソーダ水が作れるキャプテンの「レッドメロンシロップ」を紹介!!【中村商店】
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
メロンソーダとレッドメロンソーダの比較
メロンソーダとレッドメロンソーダを比較した動画がこちらです。
氷なしのクリームソーダで、アイスは浮く?浮かない?
氷なしのクリームソーダを作って
『アイスが浮くか?浮かないか?』
について実験した動画がこちらになります。
氷がある時は普通に浮いてくれますが、さて…
アイスは浮いたのでしょうか?
過去記事がこちら!
 【泡立ちにも言及!】氷なしのクリームソーダを作って、アイスが浮くのか?沈むのか?検証!!【実験】
【泡立ちにも言及!】氷なしのクリームソーダを作って、アイスが浮くのか?沈むのか?検証!!【実験】
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
自家製アイスを作るためのアイスクリームメーカーならこれがオススメ!!

クリームソーダに使うアイスは、こちらのアイスクリームメーカーを使用して作っています。
どちらも性能は同じなので、デザインで選ぶと良いでしょう!
解説動画がこちら!
詳しくは、こちらの過去動画をご覧ください。
過去記事がこちら!
 【これだけ見ればOK!】貝印のアイスクリームメーカーホワイトを徹底レビュー!!
【これだけ見ればOK!】貝印のアイスクリームメーカーホワイトを徹底レビュー!!
 【これだけ見ればOK!】貝印の「リラックマアイスクリームメーカー」を徹底レビュー!!
【これだけ見ればOK!】貝印の「リラックマアイスクリームメーカー」を徹底レビュー!!
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
【ディッシャーよりもオススメ!】アイスを球形に丸くしたい時に必要な「アイスクリームスクープ」の紹介!!

クリームソーダに乗せる丸いアイスを作りたい時は、こちらの道具を使うのがオススメです!


このように、丸いアイスが簡単に作れますよ♪

アイスをソーダ水の上に乗せるだけなので、簡単にクリームソーダが作れます♪
解説動画がこちら!
詳しくは、こちらの過去動画をご覧ください。
過去記事がこちら!
 【ディッシャーよりもオススメ!!】球形のアイスを作るための「アイスクリームスクープ」を紹介!!【ゼロール】
【ディッシャーよりもオススメ!!】球形のアイスを作るための「アイスクリームスクープ」を紹介!!【ゼロール】
詳しくは、こちらの過去記事をご覧ください。
【補足】スクープは、番号によって作れるアイスのサイズが異なるので、番号選びは必須!!

スクープもディッシャーも、番号によってサイズが大きく異なります!
アイスクリームスクープには複数の種類(番号違い)があり、それぞれで作れるアイスのサイズが変わってきてしまいます。
最初に購入する1本としては、以下の↓
こちらのサイズが断トツでオススメです!
一番平均的なサイズのアイスが作れるので、使いやすいですよ♪
ディッシャーとスクープって具体的に何が違うの?
ディッシャーとスクープの違いについては、こちらの動画でまとめておきました。
どちらも丸いアイスを作りたい時に重宝しますが、アイスの形や素材感、熱伝導率などが大きく異なります。
個人的には、スクープの使用をオススメしています。
(※理由は動画内で解説!)
過去記事がこちら!
 【これだけ見ればOK!】「ディッシャー」と「アイスクリームスクープ」の特徴や違い、それぞれの長所・短所について徹底的に解説!!
【これだけ見ればOK!】「ディッシャー」と「アイスクリームスクープ」の特徴や違い、それぞれの長所・短所について徹底的に解説!!
過去記事はこちらです。
スクープにはないディッシャーだけの魅力がある!!
、ここまでスクープばかり推してきましたが笑、実はディッシャーにしかない魅力があるんですよね。
その事についてまとめた動画がこちらです。
ディッシャーはアイス作りだけでなく、料理作りに使えます!
過去記事がこちら!
 【意外と知らない人が多い!!】ディッシャーの意外な使い道について解説!!【アイスクリーム以外】
【意外と知らない人が多い!!】ディッシャーの意外な使い道について解説!!【アイスクリーム以外】
過去記事はこちらです。
基本のあっさりバニラアイスクリーム
クリームソーダに使える基本の「あっさりバニラアイスクリームの作り方」を、こちらの動画にまとめました。
レシピ分量もアイスクリームメーカーで作りやすい量となっていて、また、生クリーム量も使い切りしやすい量になっていてオススメです。
ただし、加熱処理なしの方法となっているので、加熱処理ありの作り方については、また後日紹介していこうと思っています。
過去記事がこちら!
 【基本となるレシピを動画で解説!】基本のあっさりバニラアイスクリームのレシピと作り方を紹介!!
【基本となるレシピを動画で解説!】基本のあっさりバニラアイスクリームのレシピと作り方を紹介!!
過去記事はこちらです。